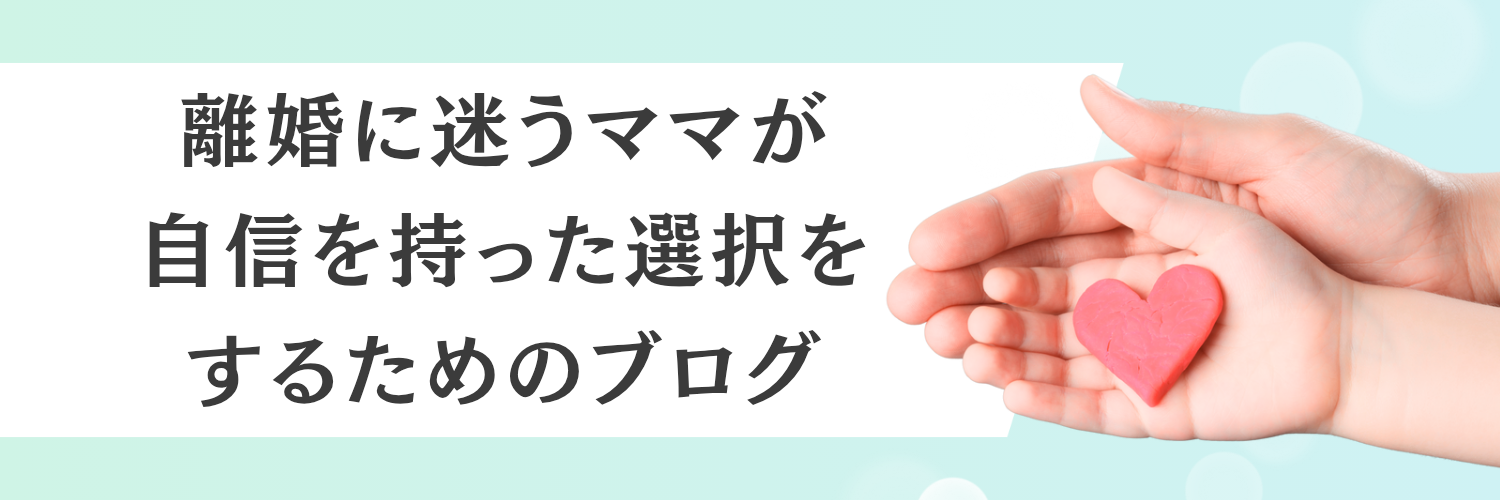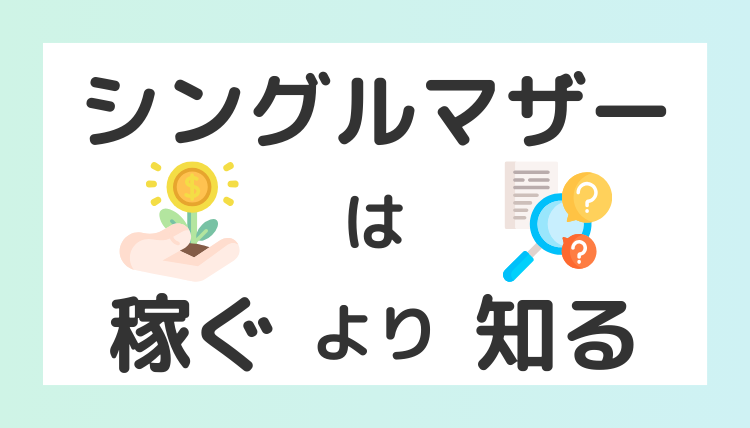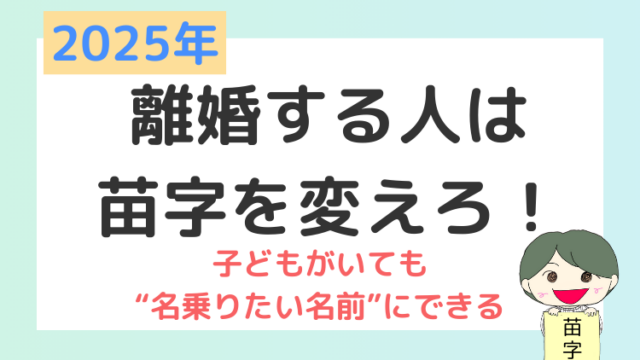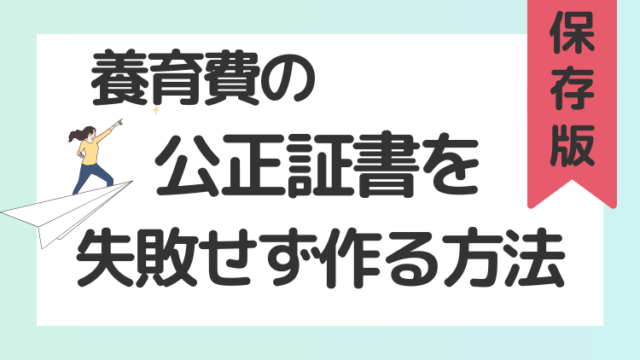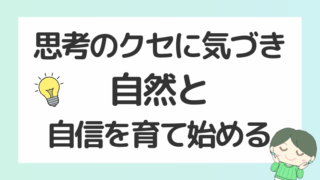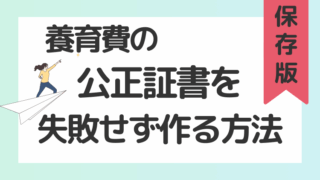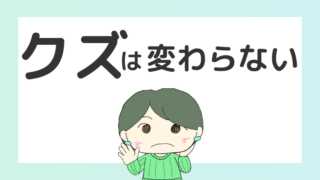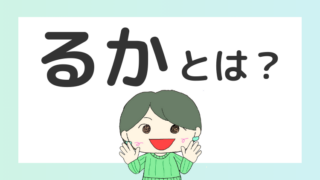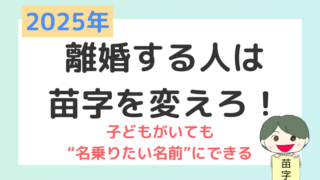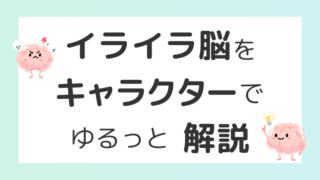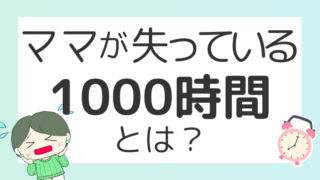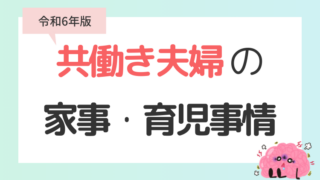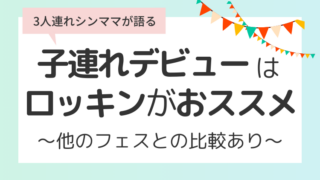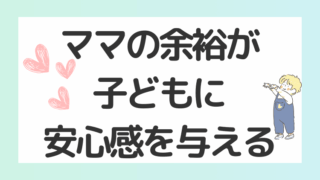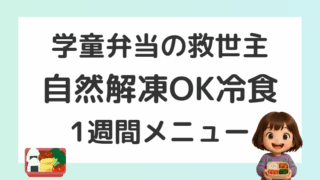夫との離婚──いよいよ現実味を帯びてきた。
でも──
「ひとりで子どもを育てて、本当にやっていけるの?」
自分から離婚を切り出す場合、養育費をきちんと貰えるかな?
経済的不安から、最終的に離婚に踏み切れずにいる方も多いのではないでしょうか?
結論、元夫からの養育費はあてになりません。
実は、全体の4割未満しか養育費を受け取れていない現状があります。
公正証書を作っても…
差し押さえするための裁判費用や時間を費やさなければならない結果から…
結局、申請せずに泣き寝入りするママ達も少なくありません。
だからこそ、養育費を頼りにせずとも生活できるための知識や工夫が必要になります。
本記事では、そんな”経済的不安”を抱えるママたちへ
実際に母子家庭が必要とする生活費はどのくらいなのか──
支援制度やシミュレーションを使って、具体的な金額を整理してお伝えします。
私自身、3人の子どもを育てているシングルマザーです。
我が家のリアルな家計も交えながら、
実際に「受け取れるお金」「足りないお金」「必要な月収」まで、具体的にお伝えしていきます。
子どもの人数別にシミュレーションできるようにしているので、
ぜひ「自分だったら…」と置きかえながら、読んでみてくださいね。
生活シミュレーション(人数別モデル表)
ここからは、実際の生活費モデルをもとに、収入と支出のバランスを数字で整理していきましょう。
しっかりと数字を見ることで、”あと1万円なら何とかできるかも”など具体的な目標に置き換えられるため、確実な自信へと繋がっていきます。
家計簿は苦手だと思う方も、簡単に計算できるエクセル表も入れていますので、活用してみてくださいね。
今回は、パート勤務や時短勤務をしている方々を想定し、給与収入手取り13万円と仮定。
支出モデルには、我が家(3人育児中)の生活費実績も参考にしながら作成しています。
以下に、子どもの人数別(最大3人まで)の月間シミュレーションをまとめました!
◆子ども1人(小学生)の場合
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 収入 | ||
| 給与(パート・手取り) | 130,000円 | 週5日・6時間勤務 |
| 児童手当 | 10,000円 | |
| 児童扶養手当 | 43,160円 | 全額支給の場合 |
| 収入合計 | 183,160円 | |
| 支出 | ||
| 住居費 | 55,000円 | 地方都市の2LDKを想定 |
| 食費 | 35,000円 | |
| 水道光熱費 | 12,000円 | |
| 通信費 | 10,000円 | スマホ・ネット |
| 教育費 | 10,000円 | 習い事を含む |
| 習い事を含む交通費 | 8,000円 | |
| 服費 | 8,000円 | |
| 娯楽・交際費 | 8,000円 | |
| 保険・医療費 | 12,000円 | |
| その他 | 5,000円 | 予備費を含む |
| 支出合計 | 173,000円 | |
| 収支差額 | +10,160円 | 少額黒字 |
◆子ども2人(小学生・中学生)の場合
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 収入 | ||
| 給与(パート・手取り) | 130,000円 | 週5日・6時間勤務 |
| 児童手当 | 20,000円 | 10,000円×2人 |
| 児童扶養手当 | 53,580円 | 全額支給の場合 |
| 収入合計 | 203,580円 | |
| 支出 | ||
| 住居費 | 60,000円 | 地方都市の3LDKを想定 |
| 食費 | 45,000円 | |
| 水道光熱費 | 15,000円 | |
| 通信費 | 12,000円 | スマホ・ネット |
| 教育費 | 25,000円 | 中学生の塾代を含む |
| 習い事を含む交通費 | 8,000円 | |
| 服費 | 12,000円 | |
| 娯楽・交際費 | 10,000円 | |
| 保険・医療費 | 15,000円 | |
| その他 | 20,000円 | 予備費を含む |
| 支出合計 | 224,000円 | |
| 収支差額 | -20,420円 | 毎月2万円の赤字 |
◆子ども3人(幼稚園児・小学生・中学生)の場合
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 収入 | ||
| 給与(パート・手取り) | 130,000円 | 週5日・6時間勤務 |
| 児童手当 | 35,000円 | 15,000円+10,000円×2人 |
| 児童扶養手当 | 60,080円 | 全額支給の場合 |
| 収入合計 | 225,080円 | |
| 支出 | ||
| 住居費 | 70,000円 | 3LDK以上必要 |
| 食費 | 60,000円 | |
| 水道光熱費 | 18,000円 | |
| 通信費 | 15,000円 | スマホ・ネット |
| 教育費 | 35,000円 | 中学生の塾代を含む |
| 習い事を含む交通費 | 12,000円 | |
| 服費 | 15,000円 | |
| 娯楽・交際費 | 12,000円 | |
| 保険・医療費 | 18,000円 | |
| その他 | 25,000円 | 18,000円 |
| 支出合計 | 280,000円 | |
| 収支差額 | -54,920円 | 毎月5.5万円の赤字 |
このシミュレーションからわかるように手取り13万円の家庭の最低限の生活費は
- 子ども1人:なんとか比較が合いそう(+10,160円/月)
- 子ども2人:あと2万円ほど必要(-20,420円/月)
- 子ども3人:あと月5.5万円ほど必要(-54,920円/月)
と、なります。
自分の実際の手取り、児童扶養手当の金額を上の表にあてはめ、参考にしてみてください!
あと数万円稼げれば良い人向けのリアル対策

赤字になる過程に関しては、副業を考える必要も出てくるかと思います。
仮になんとか生活が出来そうである家庭であったとしても、月に3,000円〜10,000円の副収入でも、収支バランスが大きく改善します。
以下に比較的始めやすい副収入の方法をご紹介します。
- スキマ時間の在宅ワーク
- データ入力(わずか800円〜1,200円程度)
- ライティング(月3,000円〜20,000円程度)
- Canvaデザイン制作(1つ500円〜10,000円程度)
- 特技を活かした副業
- 家事代行(別途1,000円〜1,500円程度)
- 子どもの送迎サービス(回数制:1回1,000円程度)
- ハンドメイド販売(利益率は商品による)
- 資格を活かした仕事
- 保育補助(勝手に1,200円程度)
- 介護ヘルパー(わずか1,300円〜1,500円程度)
- 事務・経理補助(わずか1,200円〜1,500円程度)
この中でもおすすめなのは、スキマ時間の在宅ワークです。
スキマ時間の作り方に関しては、こちらの記事もぜひご覧ください。
私自身、子どもが寝た後の夜中にデザイン作成の仕事をして月3~5万円の副収入を得ています。 最初は1つのバナー1,000円程度でしたが、実績を得ることで今では10,000円のyoutubeサムネや15,000円のちらし制作も行えるほどになりました。
母子家庭になると、夜間や休日の子どもの預け先は原則ありません。
そのため、どこかに通っての副業はハードルが高くなります。
しかし在宅ワーク副業であると、子どもたちが寝ている間に同じ家の中で行えるため、周りへの配慮を気にせずに始められます。
さらに、電気代や通信費など経費にも回せるため、実際の収入よりも所得を抑えて確定申告をすることも可能になります。そのため、収益を児童扶養手当て受給できるギリギリのバランスで経費と収益を考えて働くこともポイントのひとつです。
母子家庭おすすめの副業確定申告方法も、これから書く予定ですので楽しみにお待ちください。
家計でシミュレーションしてみよう
実際に自分の家計をシミュレーションするために、当サイトでは専用のGoogleスプレッドシートをご用意しました。以下のリンクからコピーしてお使いいただけます。
このシートでは:
- 収入(給与・手当など)の詳細入力欄
- 支出の細目別計算
- 赤字額の自動計算
- 必要な追加収入の目安表示
レシートや家計簿と照らし合わせながら使ってみてください。自分の実際の支出を入力することで、より正確な家計の状況が見えてきます。
📝印刷用シミュレーション表もダウンロードできます。
家計の見直しをじっくりやりたい方は、印刷用PDFもご活用ください。 家計の記録を1か月つけるだけでも、無駄な支出が見えてきます。
➡️印刷用家計簿シミュレーション(PDF)
母子家庭の生活費は月いくらかかる?

まず知っておきたいのは、
「実際のところ、毎月いくら必要なのか?」という点ですよね。
厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、
母子家庭の平均所得は約243万円。
これを月ベースにすると、手取りでおよそ20.2万円です。
ただし──
この「平均」は、地域・子どもの人数・年齢、そしてあなたの働き方によって大きく異なります。
だからこそ大切なのは、自分の暮らしに必要な金額を知ること。
ここからは、実際の生活費モデルをもとに、
収入と支出のバランスを数字で整理していきましょう。
リアルな月間支出モデル(首都圏・子ども2人の場合)
一般的な母子家庭(母親+子ども2人)の月間支出の目安は以下の通りです。
| 住居費 | 5〜7万円 | 地域差大、都市部は高い |
| 食費 | 4〜5万円 | 子どもの年齢の変動 |
| 水道光熱費 | 1〜1.5万円 | 季節の変動 |
| 通信費 | 1〜1.5万円 | スマホ・ネット |
| 教育費 | 1〜3万円 | 学齢により大きな変動 |
| 交通費 | 0.5〜1万円 | 通勤・通学 |
| 医療費 | 0.5〜1万円 | 助成制度あり |
| 服費 | 0.5〜1万円 | 季節の変動 |
| 娯楽・交際費 | 0.5〜1万円 | 最低限 |
| その他 | 1〜2万円 | 予備費を含む |
| 合計 | 15〜24万円 | 平均約20万円 |
| 費用目 | 金額 | 備考 |
|---|
私の場合、子ども3人(小学生1人、保育園児2人)の家計では、特に食費が月6万円前後考慮しています。 成長期の子どもの食欲は忘れられません。
この中で
住居費・水道料金・教育費・交通費・医療費・服費・保育料の7つに関しては、助成を受けられる可能性があるので、こちらの金額から下げられる可能性があります。
それでは、母子家庭含め子どもが居る家庭が受けられる手当てや助成制度・地域のサービス活用法をお伝えしていきます。
受給手当と支援制度(概要と金額)

まず、子育て世代や母子家庭には様々な受け取れる支援制度があります。
まずは、そちらをご紹介します。
私は児童手当+児童扶養手当+就学支援を受け取っており
受け取っている金額は
小学生1人・5歳児・2歳児の3人
児童手当
1人目 10,000円+2人目 10,000円+3人目 30,000円=50,000円
(上2人は3歳以上の金額)
児童扶養手当
1人目 45,550円+2人目 10,750円+3人目 10,750円=67,000円
合わせて 117,000円受給
そこに就学援助制度(小・中学生児童対象)を受給しています。
児童手当
子育て世帯全般に支給される手当なので、もう既にみなさんは受け取っている手当かと思います。みなさん、具体的に現在自分の家庭はいくら受け取っているか言えますか?
年齢や子どもの数によって金額が左右されるので、現在自分の家庭がいくら受け取っているのかをいまいちど確認してみましょう。
支給額
0〜3歳未満:月額15,000円
3歳〜小学生(第1子・第2子):月額10,000円
3歳〜小学生(第3子以降):月額15,000円
中学生:月額10,000円
支給条件
0〜15歳(中学校修了)までの児童を養育している方
(2026年度以降に18歳までの受給に変更予定)
所得制限
人数によって所得制限が変動しますが、児童2人の場合960万円未満の所得の方
児童扶養手当
ひとり親家庭を対象とした手当です。
受給には所得制限があるので要注意です!
支給額
大人1人の場合:月額44,140円(全額支給)〜10,410円(一部支給)
大人2人の場合:上記+月額10,420円
3人以降:上記+月額6,250円(1人につき)
(令和6年11月分から)
| 扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
支給条件
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方。
所得制限
受給資格者の所得に応じて支給額が変わります。
養育費を受け取っている場合には、養育費の8割を加算した加算します。
例えば)
「給与所得控除後の金額」が118万円
「養育費」4万円
だった場合には
1年間受け取っていた場合は、38万4千円(4万円×12ヶ月×0.8)を加算
そこから、社会保険料類8万円を減算
118万円+38万4千円-8万円=148万円
*我が家は昨年度育休中であったため、非課税世帯に該当するために受給しています。
| 年収(給与収入)の目安 | 1人 | 2人 | 3人 |
|---|---|---|---|
| 全額支給(満額)になる可能性が高い | ~約200万円 | ~約290万円 | ~約375万円前後 |
| 一部支給 (結果額や受給額によって段階的に減額) |
約200~360万円 | 約290~420万円 | 約375円~480万円 |
| 支給停止(受け取れない可能性が高い) | 約360万円以上 | 約420万円以上 | 約480万円以上 |
就学援助制度(学用品費・給食費などの支援)
経済的な理由で学用品や給食費の支払いが難しい家庭を対象に、必要な費用の一部を支援してくれる制度です。
小中学生のいる家庭が対象で、ひとり親家庭も多く利用しています。
対象者
生活保護を受けていないが、それに準じる所得水準の世帯
非課税世帯や、住民税の一定額以下の家庭が対象となることが多いです。
ひとり親家庭は該当しやすい傾向にあります。
支援内容
学用品費、給食費、通学費、校外活動費、新入学学用品費、修学旅行費など
支給額や支給時期は自治体によって異なります。
一部の自治体では、クラブ活動費や医療費を支援する場合もあります。
支給方法
年度初めまたは学期ごとに分けて支給されることが多く、
支給は現金で行われる場合や、学校を通じて直接処理されることもあります。
ひとり親家庭等医療費助成
対象者
ひとり親家庭の親とその子ども
※自治体によっては、親が対象外の場合もあります。
対象年齢
中学卒業まで、高校卒業までなど、自治体によって異なります。
助成内容
医療機関の窓口で支払う自己負担分(3割)を、全額または一部助成してもらえます。
実質、医療費が無料になる自治体もあります(所得制限あり)
*児童扶養手当の所得制限と概ね同じ傾向にあるようです。
ここまでの制度に関して申請方法など詳しいことはこちらの記事に記載しておりますので合わせてご覧ください。
保育料の支援と軽減措置
離婚によって世帯年収が下がり、住民税の額も低くなると、保育料も軽減される可能性が高いです。
3〜5歳の子どもに関しては、すでに「幼児教育・保育の無償化」がスタートしていますが、食費や備品代は掛かっています。
所得が下がるとその中の副菜の費用も軽減されることがあります。
また、0〜2歳のお子さんについても、
住民税非課税世帯であれば、保育料が全額免除になるケースもあります。
本来は年度内で決まった期間での所得計算をして、保育園料を出していますが、離婚やり職など保護者の事情によっては申請をすればすみやかに保育料の見直しをしてもらえます。
その場合には、自治体へ 就労証明書や課税証明書などを提出して再算定してもらう必要があります。
高等学校等就学支援金制度
この制度は、国公私立問わず高等学校等に通う生徒の授業料負担を軽減するためのものです。
支給額
公立高校全日制:月額9,900円(年額118,800円)
私立高校:世帯年収に応じて月額9,900円または33,000円
所得要件
年収約590万円未満:月額33,000円
年収約910万円未満:月額9,900円
年収約910万円以上:対象外
申請方法
在籍する学校を通じて申請。オンライン申請システム「e-Shien」を利用
高等教育の修学支援新制度
大学や専門学校などの高等教育機関への進学を支援する制度です。
支援内容
授業料・入学金の減免
支給額の例(住民税非課税世帯の場合)
私立大学:授業料最大70万円、入学金最大26万円
給付型奨学金:月額最大75,800円(自宅外通学の場合)
所得要件
住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯が対象
申請方法
進学先の学校を通じて申請。
詳細は日本学生支援機構(JASSO)のウェブサイトを参照ください。
習い事や塾代について
習い事や塾などの費用については、基本的に公的な支援制度の対象外となります。
ただし、自治体によっては独自の助成制度を設けている場合があります。
また、地域の子ども食堂や学習支援ボランティアなど、無料または低料金で利用できるサービスも存在します。市や町内会で発行されている会報や、地域の情報を発信しているSNSをチェックすることをおすすめします。
私は、子ども食堂や衣類の無料配布情報、小学校の体育館や町役場で開催されている習い事を駆使して生活しています。
その他の支援制度
- JR通勤定期券割引:JRの通勤定期が3割引になる制度 *JRで定期券を購入時に手続き
- 住宅手当・家賃補助:地域によって異なる住居費支援 *市町村町役場で手続き
- 水道料金の助成:自治体によって異なる光熱費支援 *市町村町役場で手続き
ここまでご覧いただいて、いかがでしたか?
所得による制限も多いのですが、これだけ多くの金銭的な支援が活用できることをご理解いただけたかと思います。
特に一番心配となるであろう子どもたちの学費に関しては、大学進学迄も見越した制度も出ていますので、母が一人身を粉にして働かなければ通わせられない時代ではなくなったと言えます。
では次に、具体的に掛かってくる生活費のシミュレーションを人数別モデルで見ていきましょう。自分の家庭にあてはめ、よりリアルに想像をしてみて下さい。
離婚後の生活に向けて今しておくべきこと
 離婚後に生活面を安定させるためにも、事前に出来る限りの準備をすることをおすすめします。
離婚後に生活面を安定させるためにも、事前に出来る限りの準備をすることをおすすめします。
支援制度の申請準備
- 必要書類を事前に確認する
- 住民票、戸籍謄本、結果証明書などを準備する
- 自治体によって必要な書類が異なるため確認を
- 申請タイミングを押さえる
- 児童扶養手当:離婚当日から申請可能(元夫と住民票地が別でなければ申請できないので要注意)
- 医療費助成:児童扶養手当と同時に申請可能
- 窓口の場所と開庁時間を調べておく
- 土曜日にも対応しているところもあるので、確認をしていく日を確保しておきましょう。
家計の見直し
- 固定費の見直しをする
- 携帯電話プランの見直し(格安SIMへの乗り換えで月3,000円〜5,000円削減)
- いらない保険や契約の見直し
- サブスクリプションサービスの整理
- 節約習慣をつける
- 電気・ガス・水道の使用量削減
- 食費の工夫(男の子、食材のムダをなくす)
- ポイント活用の習慣化
副収入の準備
- 現在のスキルで始められる副業を探す
- ソークラウドシングサイトに登録
- 副業可能な職場環境か確認
- スキルを磨く
- 資格取得(離婚後母子家庭自立支援給付金制度を活用できる様に市区町村町役場に相談へ行く)
- オンライン講座などでスキルアップ
相談相手・支援者を見つける
- 公的相談窓口を知っておく
- 母子・父子自立支援員(各自治体に配置)
- ハローワーク(母子家庭等相談・自立支援センター)
- 法テラス(法律相談)
- 同じ立場の仲間を見つける
- シングルマザーの交流会や情報交換の場
- オンラインコミュニティへの参加
私自身、離婚前に母子自立支援員に相談したことで、知らなかった支援制度の情報を得ました。相談できる相手がいるだけで、精神的にも大きな支えになります。
まとめ|生活は「できる」でも、知らなきゃ損
母子家庭の生活は、楽とは言えません。
しかし、正しい知識と準備があれば、十分に乗り越えられるものです。
多くの行政支援制度は、申請しなければ受給できません。
だからこそ、最大限活用するには、事前の情報収集と計画が不可欠です。
生活費を現実的に想定し、足りない部分に対する補填策を考えること。
収支のシミュレーションを行い、必要な収入額を明確にしましょう。
ここまで読んでくださったあなた。
きっと今、情報量の多さに少し疲れているかもしれません。
でも安心してください。
すべてを一度に完璧にやる必要はありません。
できることから少しずつ、そして着実に。
しかし──
「無理なく始めよう」とだけ思っていても、実際には何も変わらないのも現実です。
だから、今日。
小さな一歩だけ踏み出してみませんか?
今日できる一歩は、とてもシンプルです。
エクセル版・またはPDF版のシートを手に取り、あなた自身の「今の家計」と「これから必要な収入」を見える化してみましょう。
副業の種類については、こちらの記事も参考にしてくださいね。
不安に支配されず、自分と子どもたちの未来を守るために。
情報を持ち、準備をして、
あなた自身の未来を自分の手に取り戻していきましょう。
この記事が、不安を恐れず一歩踏み出すママたちの勇気になりますように。